 Cestaハウス と 空に月ハウス
Cestaハウス と 空に月ハウス
- 2017.1.20
- |BLOG
それぞれ現場が進みます。
この日は寒かったです。
屋根の上に昇って板金業者さんと
詳細図を見ながら納まりの打ち合わせ。
冬は寒いし、夏は照り返しで暑いし・・・
屋根工事を行う板金職人さんは本当に大変かと思います。
10時の休憩時間は暖かいコーヒーで
一休み・・・。
この寒い中、浦野棟梁は2人の大工さんとどんどん仕事を進めていきます。
午後からは空に月ハウスの現場へ
施工は創建舎さんです。
1階RC部分の型枠を組んでいます。
外部はコンクリート打ち放し仕上げのため、
型枠の割り付けやセパレーター(型枠を固定する道具)の位置が
そのままコンクリートに出てくるため、
全て寸法を決めてきれいに見えるようにしています。
裏手は型枠を鉄パイプでしっかり固定して
コンクリートを流し込んでもずれないようにしています。
こちらも職人さん達にアドバイスをもらいながら
細かい部分のすり合わせを行いました。

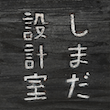
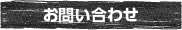



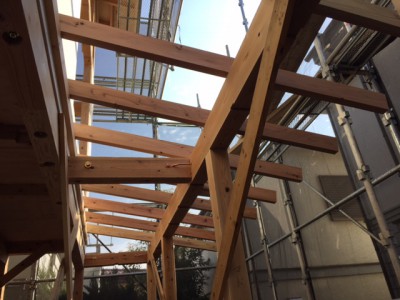




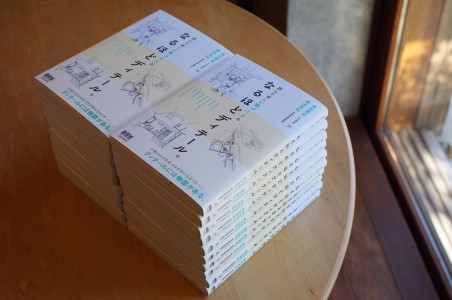









 カテゴリー
カテゴリー